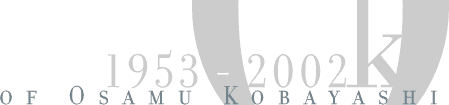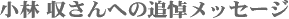|
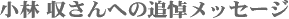


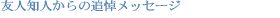
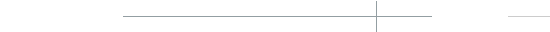
彼は最後まで忘れなかった
■藤田俊一(前「日経パソコン」編集長)
「俺たち、こんなことをしていて本当にいいのかねえ」
昨年の秋、9月11日のテロ事件があってから1カ月経つか経たないかのころだっただろうか。ある会合の帰り、エレベーターを待っているときに小林がふっと呟いた。何と答えたかは覚えていない。この混迷の時代に、メディアは、いや自分はやるべきことやっているのだろうか。その問いかけには黙るしかなかったような気がする。
七七日の後、光代夫人からいただいた御挨拶状の中に「男は日本の国を良くする為に働くんだと学生時代に格好付けていっていた」とあるのを見て、ああ、と思った。小林もそう思っていたんだ。この歳になったら、気恥ずかしくて言えないけれど、この職業を選んだ人間ならば、大なり小なり、そうした気持ちが持っていた。もう遙か遠い昔の学生時代の気概。それを小林は心の奥にずっと持ち続けていた。
小林とは日本経済新聞社の同期入社だったが、本当に親しくなったのは1990年、彼が産業部の商社担当キャップ、僕が証券部の会社担当キャップのときだった。記者の世界は他紙と競争すると同時に内部での競争も激しいから、とかく情報を抱え込みがちだ。しかし、彼は「産業部、証券部どちらが書いたって日経が勝てばいいじゃないか」と言って、情報交換を緊密にしようと提案してきた。全く同感だったので、この話にはすぐに乗った。
その1年の付き合いで、彼のことがよくわかった。以来、小林を人に紹介するときの言葉は決まっていた。「私が最も信頼している人間。信じて裏切られることはない」。だから、日経パソコンの編集長になった98年の春、小林が次期編集長として日経ビジネスにやってきたときは、本当にうれしかった。ふたつの雑誌は社内では部数を競い合う関係にあったが、日経BPとして良いことならば、それは良いことではないかと、いろいろなことを話し合い、相談した。
そのころの小林を近くで見ていると、日々成長し、人間として大きくなっていくのがわかった。「自信家」とか、「目立ちがり屋」とかいう声もあったが、内面に秘めた繊細さと、それを押し殺しても進む責任感の強さをかいま見ることが何度かあり、そのたびに胸を突かれる思いがした。
日経ビジネスの大躍進も日経MJのリニューアルも卓越した業績だが、小林の本当の仕事はこれからのはずだった。ジャーナリズムとコマーシャリズムの両立というメディア・ビジネスの綱渡りができる、数少ない人物と思えたからだ。「商売」の責任を果たす一方で、「自分はこれで本当にいいのか」と自問するジャーナリストの精神を失っていなかった。
「俺たち、こんなことをしていて本当にいいのかねえ」
小林の問いかけはいまも耳の奥に残っている。
「まあ、僕としてはやれるだけのことはやったと思うよ」
今度は沈黙せずに、その程度は言えるようになりたいと思う。それが残された者の責任なのだろう。
>> 次のメッセージへ進む
このサイト上の各コンテンツの著作権は小林収メモリアルサイト制作グループもしくは、このサイトにコンテンツを提供していただいた各企業、各寄稿者に帰属します。無断転載はお断りいたします。
Copyright: 2002 Kobayashi Osamu Memorial, associated companies and writersAll Rights Reserved.
このサイトに関するお問い合わせはinfo@kobayashiosamu.net までお願いいたします。
Designed by BlueBeagle LLC
|