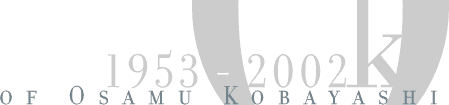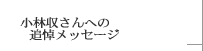|
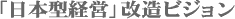






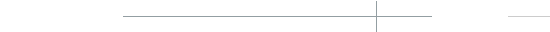
トップの報酬に明確な格差を
新潮社「フォーサイト」1995年2月号掲載
一時は世界を席巻するかに見えた「日本型経営」が色あせている。バブル崩壊で日本企業の競争力自体にかげりが出るにつれて、日本の経営者は急速に自信を失い、「リエンジニアリング(業務の根本的革新)」がブームになったように、蘇生してきた「米国流」を企業が見直し始めている。とはいえ、ほんの少し前まで「人を大事にするのが日本流」と言っていた企業が一転、「果断なリストラ」を叫ぶのは、いくらなんでも定見が無さすぎる。
日本流の良さを残しながら、いかに競争力を回復して行くべきか。国内、海外で企業を見てきた一ジャーナリストの視点から、日本型経営の改造を考えてみたい。
家すら持てない「日本の社長」
日本の新聞、テレビの取材活動で、世界的にみてほぼ例の無いのが「夜討ち」だ。
夜も更けてから政治家、役人、企業経営者などの自宅を訪れ、直接取材するもので、昼(建て前)と夜(本音)の世界が分かれている日本ならではの制度である。プライバシーを重視する欧米では考えられない。旧知の米人記者は「こんな恵まれた慣習がある割には、日本のジャーナリズムからは大スクープが出ない」と皮肉るが、日本の記者にとって取材の大きな武器になっていることは確かである。
その夜討ちが、企業取材に関して、とみに〝効率〟が落ちている。原因は首都圏の住宅事情だ。社長以下の経営首脳の私邸は、いわば「遠・狭・高」。都心からより遠く、より狭く、そしてしばしば戸建てではなく、高層マンションに変わってきた。出向いて行くのに時間がかかるし、住居が狭ければじっくり話し込むのも御家族に気兼ねする。
筆者が駆け出しの頃、日本精工のトップで当時、「財界の政治部長」と言われた故・今里広記氏の自宅を夜討ちしたことがある。東京・渋谷区の閑静な住宅街の広い純日本式の邸宅で、玄関から上がったところに六畳ほどの渋い待合い室があった。それほど重要でない客(つまり当時の筆者のような)は奥の応接間ではなく、ここに通されたようだ。
今、こんな家に住んでいる企業のトップはまず存在しない。夜討ちに行って記者が唸るような豪邸は、オーナー経営者の住居か、社長ではなく企業が所有者の「社宅」か、さもなくば「本人か奥方の実家が代々の大金持ち」の場合に限られている。
首都圏の地価が高すぎることもあるが、社長の給料の方も安過ぎるのだ。日本人の大多数はサラリーマンである。それが社長になっても自力では大した家一軒立たないのだとすると、やる気を削ぐことおびただしい。
毎年五月頃、米国の有力経済紙である「フォーブス」や「フォーチュン」は企業の最高経営責任者(CEO)の所得番付を載せる。九三年度の全米トップになったウォルト・ディズニー社のマイケル・アイズナー会長の稼ぎは二億三百二万ドル(約二百億円)に達した。二百億円! これは日本のサラリーマン社長の約五百人分の年収の合計に相当する。
二億ドルというのは米国でも飛び抜けているが、フォーブス誌によると、この五年間で計五千万ドル(約五十億円)以上の報酬を得たトップは、十人に達した。平均的には年収二百万~三百万ドルというところで、日本の社長の五、六倍はもらっている。
米国内にはCEOの高額報酬への批判もある。九一年には経営評論家のグレイフ・クリスタル氏が『イン・サーチ・オブ・エクセス(過剰の研究)』(題名はトム・ピーターズ氏の『イン・サーチ・オブ・エクセレンス』=邦訳エクセレント・カンパニー=のもじり)を出版、大きな話題となった。
米のCEOの報酬は「サラリー」、「ボーナス」、「ストック・オプション(株式買取権)の供与」の三種からなっている。オプションは一定の価格で自社株を購入できる権利であり、CEOの在任中に株価が上昇すれば、権利行使で巨額の利益が入る。アイズナー会長の場合、子会社のユーロディズニーの不振から九三年のサラリーとボーナスは計七十五万ドルと一挙に前年の十分の一に減額されており、総報酬の九九%はこれまでに付与されてきたオプションの行使から得ている。
番付を載せたフォーブス誌はアイズナー会長の報酬額に対し、「これはもらい過ぎか」と問いかけた後、しかし、こう記している。
「アイズナーがCEOだったこの十年弱で、ディズニーの株価は六倍になった。同社は年金基金が大株主であり、彼の経営手腕は、この基金から年金を受け取る一般の人々に多大の恩恵を与えている」
米国流の考え方のポイントは次の三点だ。
①企業の価値(通常は株式時価総額)は経営トップの能力次第で大きく変わる。
②できるトップに高額の報酬が与えられるのは当然。
③報酬の中身はディスクロージャー(情報公開)しなければならない。
これに対し、日本では「企業の価値を高めるのはトップではなく社員全員の努力」と考えられがちだ。従って、トップの報酬は一般社員からかけ離れたものにはできず、業界の横にらみなどで決められてきた。
日本人のメンタリティーにこうした一種の平等主義が合うのは確かだろう。だが、これではプロの経営者はなかなか育たない。企業経営には時として大幅な人員削減など「血を見る」決断が必要だが、今の日本ではそうした外科手術をしたトップに対し、正当に報いるシステムが無いのである。
ある企業が不採算事業からの撤退とそれに伴う大量の希望退職募集を決めたとしよう。米国なら収益好転を見越して株価が上昇し、経営者はストック・オプションで自分も潤う。一方、日本では経営者は良くてボーナス返上、場合によっては自らの進退伺いを出さないと世間が納まらない。
できるリーダーには報いよ
もう一つの日本の問題は、表向きの給与では「社長の体面」が保てないとして〝裏の報酬〟が出てくることだ。社長社宅がそうだし、高級ゴルフ場の会員権、専用車と運転手、高級料亭などの利用と枚挙に暇がない。
この裏の報酬の存在が、日本で経営陣の交代が遅れがちになる大きな原因だ。一線を引いたとたん、社の豪邸を追い出され、会員権と車が取り上げられてしまえば、生活レベルは一挙に低下してしまう。ある大手企業の秘書室長は「ゴルフ会員権は死ぬまで使う、とゴネる人が多い」と苦笑する。
逆に、成功裡に引退した米国経営者の老後はたいへん優雅だ。たとえば、日本でも有名なリー・アイアコッカ氏(クライスラー前会長)やジョン・ヤング氏(ヒューレット・パッカード前社長)は、いずれもベンチャーキャピタリストとして有望企業の育成に力を注いでいる。地域社会などに多額の寄付をする元CEOも数多い。
日本人はリーダーシップに欠ける、との見方がある。問題なのは、リーダーシップを発揮して良い結果をもたらした人に公明正大に報いるシステムがないことである。能力給などミドル層の人事制度は見直しが始まっているが、本当に重要なのはトップに対する報酬制度の改革だ。
日本でも企業の自社株買いが解禁される見通しになった。これで購入した株がストック・オプションの原資になる。今のところ自社株買いは「株価維持」の観点でしか議論になっていないが、早急に経営幹部に対するストック・オプションの導入を検討すべきだろう。できるリーダーとできないリーダーをはっきり選別していかない限り、日本企業、さらには日本社会の体質は改善して行かない。
このサイト上の各コンテンツの著作権は小林収メモリアルサイト制作グループもしくは、このサイトにコンテンツを提供していただいた各企業、各寄稿者に帰属します。無断転載はお断りいたします。
Copyright: 2002 Kobayashi Osamu Memorial, associated companies and writersAll Rights Reserved.
このサイトに関するお問い合わせはinfo@kobayashiosamu.net までお願いいたします。
Designed by BlueBeagle LLC
|