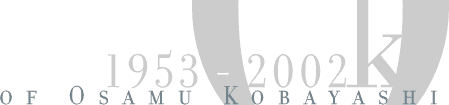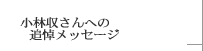|
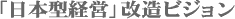






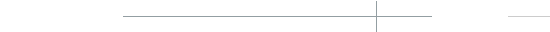
猫の首に鈴を付ける法
新潮社「フォーサイト」1997年7月号
株主総会を前にして企業の不祥事が相次いでいる。今年、特に目だつのは「中興の祖」や「実力会長」に絡んだスキャンダルの多さだ。
全日本空輸の若狭得治取締役名誉会長(八二)、味の素の鈴木三郎助取締役名誉会長(七四)、野村證券の田淵節也取締役相談役(七三)。そして、第一勧業銀行でも、総会屋との付き合いの発端は旧第一と旧日本勧業の合併の立役者だった故井上薫会長時代にあった、との指摘が出てきている。
若狭、鈴木、田淵の三氏が経営者として出色だったことは誰もが認める。若狭氏がいなければ、全日空の国際線の進出は実現しなかったかもしれない。創業者の直系である鈴木氏の下で、味の素は所有と経営の分離が進んだ。田淵氏の時代に野村は証券界のガリバーになった。だが、この三氏が晩節を汚したことも、また、事実なのである。
これは本人はもとより、企業にとっても不幸である。功なり名遂げたトップにいかに有終の美を飾らせるか、その方法論を考えるべき時に来ている。
マスコミはトップの倫理観を声高に叫ぶが、精神論だけで片づく問題ではない。中興の祖に対し現役の社長が完全引退を促すのは、猫の首に鼠が鈴を付けるようなものだ。実際、若狭氏という「猫」の猛反撃にあって、「鼠(普勝清治全日空社長)」は自らの退陣表明を余儀なくされた。必要なのは、「猫の首に鈴を付ける」ためのきちんとした制度である。
「アメとムチ」で老害を減らせ
第一は、取締役の定年制だ。
社長業は肉体的、精神的に激務だから、七十歳が近づけばたいていの人は自分から「第一線を退く」と言い出す。問題はこのあとだ。社長として実績をあげた人ほど、会長、さらに取締役相談役に退いてからも「実権」、特に「人事権」を完全には手放したがらない。
高齢化した中興の祖たちは、最新のテクノロジーの動向にはついて行けなくなっても、「人事なら俺の方が詳しい」という意識を強く持っている。なにしろ、現役の役員や部長クラスがまだ駆け出し同然の頃から、企業経営に携わってきたのだから。
だが、「麒麟も老いては駑馬に劣る」のたとえ通り、彼らが影響力を持っている限り、企業の新陳代謝は大きく損なわれる。人事評価で「昔のイメージ」がなかなか払拭できなくなるし、彼ら自身の行動力が鈍ってくる結果として、往々にして周囲に「側近」という名の「茶坊主」グループが発生する。
これを阻止するには、取締役に定年制を設けるしかない。
例えば七十歳とか七十二歳を上限にしておけば、会長に退いてから通常は数年で役員でなくなってしまう。もし、野村證券が役員定年制を敷いておれば、七十歳を超えた田淵節也氏を〝復権〟のために、無理に取締役に戻さずに済んだ。
取締役でなければ、法的には企業経営に対して何の権限もなくなる。役員会にも出席できない。どんな実力者であっても、徐々に影響力はフェードアウトして行く。肩書きが(取締役でない)名誉会長、相談役、最高顧問などと立派に響いても、しょせんは名誉職だ。ちょうどその頃には、国からの叙勲(七十歳以上)もあるだろうから、完全引退への道は整う。
第二は自分の会社への息子、娘婿の入社禁止だ。
オーナー企業を別にすれば、経営者が息子や娘婿を自分の会社や子会社に入社させてロクな結果になったことがない。自分の影響力が失われれば息子や娘婿の将来が危ないと懸念して、経営者に居座りの動機が生まれる。「しょせん七光」としか見てもらえない子供の方も本当は不幸なのだが、いったん入社させれば、名経営者ですら単なる親バカに変わってしまう。
今回の全日空騒動でも、若狭氏が長男を子会社のホテルの社長に据えたことが発覚して、一気に氏への評価が下落した。以前にも大蔵省の元高官が、娘婿の大蔵官僚の名義でサラ金の未公開株を取得したとのスキャンダルがあった。米国のように「親と子は別人格」というのが徹底していればいいが、日本のウェットな社会では、「子息の入社は禁止」という制度を設けなければ老害とネポティズム(親族びいき)の根は絶てない。
第三に役員の報酬制度の整備がある。
日本企業のトップがなかなか完全引退しない理由の一つに〝薄給〟がある。会社が支払う潤沢な交際費、差し向けるハイヤー、自由に使えるゴルフ会員権などを除くと、給与そのものはトップといえども意外に大したことがない。完全引退でこれらの特典がはずされれば、生活レベルは一気に下落してしまう。引退しないのではなく、引退できない、との側面もあるのだ。
日本でも役員に対するストック・オプション(自社株買い取り権)が導入されるなど制度整備が進み始めたが、まだ十分ではない。「中興の祖」と言われたほどのトップなら、それこそ完全引退と引き替えに、十億円単位の「退職金」や年間数千万円の「終身年金」などを与えて然るべきではないか。従業員に早期退職金割増制度があるのだから、役員にもそれがあってもいいかもしれない。
もちろん、「お手盛り」と言われないよう、明確な基準作りとディスクロージャー(情報開示)は欠かせない。日本長期信用銀行の頭取、会長、取締役最高顧問として二十年近く君臨した杉浦敏介氏への退職金について、『選択』誌の六月号は「二十五億円」という数字を伝えている。バブルへの対応を大きく誤った銀行のトップへの退職金としては目を疑う数字だ。長銀が正確な数字の公表を避けているのも、輪をかけて問題である。
現在の役員退職金は単純に取締役の在任期間で決められているケースが多い。だが、従業員と違って経営者は、年月ではなく、企業の利益や株式時価総額をどれだけ増やしたかで評価するのが本筋である。長銀の株価は四百円を割って低迷しており、時価総額基準で考えるなら、とてもトップに億円単位の退職金を払うような状況ではない。
トップに対して定年制やネポティズム禁止といったタガをはめる一方で、評価すべき人に対しては十分な退職金を用意する。このアメとムチの制度整備によって老害は相当程度減るはずだ。
ワトソン二世の「引退の美学」
だが、それでも最後には引退の美学とでも言うべきものが残る。資本主義経済のメッカである米国の企業社会においても、日本で考えられる以上に引き際の美しさ、潔さは貴ばれている。
最も美しい引退劇として今なお伝えられているのは、IBMの二代目最高経営責任者(CEO)だったトーマス・ワトソン二世である。創業者のワトソン一世の後を継いでIBMの黄金時代を築いたが、一九六六年に役員の六十歳定年制を採用。自分はそれに三年残した五十七歳でCEOを引退した。子息はIBMに入れず、ワトソン家とIBMの関係を自分の代で断ちきった。
引退後は、他の大企業の社外取締役を務める一方、政府の委員、市民団体の役員、大学の評議会の理事として活動した。後に請われて、十人余りいたIBMの社外取締役の一人になるが、経営に対しては一切、口を挟まなかったという。
ワトソン二世は『ザ・ヒーローズ・フェアウエル』(J・ソネンフェルド著、吉野壯兒訳、邦題『トップ・リーダーの引退』)でこう語っている。
「一般的にいって、六十歳でCEOを辞めた人間が、フルタイムの役員や会長としてとどまるのを許すのは間違いだと思う。発揮さるべき新しい経営者の能力を弱めてしまうからだ。前のCEOが社内でうろうろするようなことが少なければ少ないほど、いっそうよい」――と。
このサイト上の各コンテンツの著作権は小林収メモリアルサイト制作グループもしくは、このサイトにコンテンツを提供していただいた各企業、各寄稿者に帰属します。無断転載はお断りいたします。
Copyright: 2002 Kobayashi Osamu Memorial, associated companies and writersAll Rights Reserved.
このサイトに関するお問い合わせはinfo@kobayashiosamu.net までお願いいたします。
Designed by BlueBeagle LLC
|