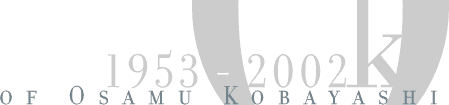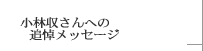|
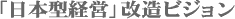






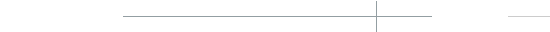
さらば悲観論! 日本の「強さ」を今こそ見直そう
新潮社「フォーサイト」1998年1月号
一時は世界を席巻するかに見えた「日本型経営」が色あせている。経営者は急速に自信を失い、蘇生してきた「米国流」を見直し始めている……。
今からちょうど三年前、筆者はこのコラムの第一回をこんなふうに書き出している。それから三年の間に、日本の自信喪失状態はさらにひどくなったようだ。昨年は山一證券、北海道拓殖銀行を含め戦後初めて、二桁の上場企業が事実上、倒産した。金融不況の病はアジアに飛び火する一方で、米国はドル高・株高・好景気という我が世の春を謳歌している。
だが、日本経済はそんなに弱いのか。逆に米国はそれほど強いのか。連載を終えるにあたって、本当に今が日本にとって「第二の敗戦」なのかどうか、考えてみたい。
米国流「株主資本主義」の弱点
まずは、現状の日米の力関係を見てみよう。
米経済紙『フォーチュン』は毎年、「フォーチュン500」の世界版を公表する。米国だけでなく、日本や欧州を含めた全世界ベースでの売り上げによる企業番付である。その業種別ランキングを見ると、日本企業の存在感の高さがはっきりする。
業種は保険を生保、損保の二種に整理すると、全部で四十二。そのうち、日本企業がトップの座にあるのは別表の十一分野を数える。ちなみに、米国は十九、欧州は全体で十にとどまっている。
しかも、日本がトップの分野は「看板」である自動車や電機ではない。製造業では機械、金属、ゴムといった比較的地味な産業だし、八分野まではサービス産業である。
もちろん、売り上げだけが企業の力を示す物差しではない。東京三菱は、世界「最大」ではあっても決して「最強」の銀行とは言えない。ただ、企業において規模はやはり力である。世界最大の「機械」「金属」「ゴム」「旅行代理店」「生保」「鉄道」「通信」「電力」――が日本にあることは、紛れもない事実なのだ。
こうした分野で米国勢の影が薄い理由は、はっきりしている。もうからないからだ。
株主の力が強い米国では、優良企業の条件は「ROE(株主資本利益率)二〇%」の確保である。それが達成できなければ経営者への風当たりは強くなる。だが、ハイテク分野ならいざしらず、地味な素材メーカーや公益性のあるサービス産業でこのハードルを超すのは容易ではない。
結果として、米国ではこうした分野にはカネが回りにくく、それがR&D(研究開発)や設備投資を沈滞させるという悪循環に入っている。米国の資本はシリコンバレーなどに群生するハイテクベンチャーに熱い眼差しを向ける反面、在来産業に対しては利益回収重視で投資を控えている。
復活したかに見える米国産業には、いくつか見逃せない〝黒点〟が出てきている。日本の投資と技術でかろうじて命脈を保っている鉄鋼業が代表格だ。部品から素材まで幅広い要素技術が必要な自動車で、今なお米ビッグスリーが品質で日本車を上回れないのも、そこに理由がある。
米『ビジネスウィーク』誌は九七年十二月一日号で、「若い世代のアメリカ人のビッグスリー離れが進んでいる」と指摘。ベビーブーム世代(三十三歳―五十三歳)では「米国車好み」の四四・〇%に対し「アジア車=日本車好み」が四五・八%と逆転、X世代(十八歳―三十二歳)になると四一・一%対四九・四%と差がさらに開くとの調査結果を載せた。
マクロ経済を見ても、日本が弱くて米国が強い、とは言いきれない。
確かに米国経済はインフレなき成長を続け、失業率は低く、株価も高値圏を維持している。だが一つ、改善どころか悪化の一途をたどっている重要な指標がある。経常収支だ。
米国の経常収支赤字はレーガン政権時代の一九八七年、千六百八十億ドルという巨額に達し、「財政、貿易の双子の赤字」が最大の問題とされた。その後、ドル安政策もあって経常赤字は減少に転じたが、米国の競争力復活が言われ始めた九四年辺りから目だって増加している。ドル高の効果が本格化する九七年か九八年には、米国の経常赤字は二千億ドル規模と十年ぶりに史上最大になるとみられる。
財政赤字については財政改革法案などで削減のメドをたてた米国が、双子の「片割れ」をなぜ制御できないのか。それは産業分野における〝黒点〟の存在と同じ理由だ。「ROE二〇%の呪縛」である。
企業は景気変動に備えてある程度の余剰生産設備を持つのが普通だが、ROEを重視すれば、余剰分は小さいほどいい。日本や韓国のように不況期に輸出ドライブが働くというメカニズムは乏しく、ヒトも設備も効率重視というリーン経営(スリムな経営)がもてはやされている。さらに、海外で生産した方がコストが安いなら国内生産にはこだわらない。
結果としてこの十年間、米国のモノ(財)の輸入は、景気循環とは関係なく、ほぼ一貫して増え続けている。米国流の株主資本主義にあっては、もうからない産業は空洞化が避けられないのだ。
タイ、インドネシアなど東南アジア各国が昨年後半、通貨・経済危機にひんした際、経常収支の赤字を海外からの資金流入(資本収支の黒字)でまかなってきた脆弱な構造が問題だとされた。その分析は正しいが、実は米国は全く同じ国際収支構造を持っている。
唯一、最大の違いはドル=国際通貨という一点にある。この「共同幻想」に少しでもひびが入れば、米国は危うい。一方で日本は一千億ドル規模の経常収支の黒字を続け、外貨準備だけで二千二百億ドルに達している。ここ一年ほどの為替相場を見て、ドル=米国が強く円=日本が弱い、と単純に決めつけるのは間違っている。
日本優位の「デジタル家電」
次に「日米戦争」の〝舞台〟を点検してみよう。
日本が米国に決定的に遅れをとったと思われているのが、インターネットに代表される「サイバースペース(電脳空間)」の世界である。
ここではインテル、マイクロソフトの「ウィンテル」が世界標準(グローバルスタンダード)を固め、シリコンバレーからベンチャーが続々と育つ。変化は「ドッグイヤー(犬の時間=人間の七倍の早さ)」のスピードで進み、公用語は英語。こんな図式を示されて、自信喪失に陥った日本企業は少なくない。
もちろん、米国がトップランナーだというのは事実だが、本当に日本の出番はないのか――。
ここ一、二年、米ハイテク企業の経営トップの動きで、目だって変わったことが一つある。来日回数の増加だ。新聞・雑誌の個別インタビューにマイクロソフトのビル・ゲイツ会長が登場する機会は、ひょっとすると日本の方が本国より多いかもしれない。
日本がマーケットとして巨大だということもあるが、それだけならゲイツ会長ほどの多忙なトップが自ら頻繁に来るには及ばない。理由は日本企業との幅広い提携、協力関係の構築にある。
キーワードは「デジタル家電」だ。サイバースペースは当初のハイテク機器の操作に熟達した人たちの世界から、ごく一般の消費者を巻き込んだものへと拡大・進化しつつある。それに伴い、機器、端末の操作は誰でも簡単に使える「バカチョン性」が必要になってきた。つまり、パソコンの家電化である。
コンピューターならIBM以来、米国のお家芸だが、家電となると話は別だ。米国の家電のルーツとも言えるRCA(ラジオ・カンパニー・オブ・アメリカ)はGE(ゼネラル・エレクトリック)、仏トムソンと次々身売りを余儀なくされ、ブランドこそ残っているものの、企業としては見る影もない。テレビ、オーディオなどのAV機器は米国産業の〝黒点〟なのである。
日本ではデジタル家電を意識した新製品が次々と登場してきている。例えば、茶の間でテレビとインターネットを同時に楽しめるインターネットテレビだ。ソニーは昨年十一月、インターネットの画面が現れるスピードが早く、かつアダプターも四万五千円と手軽な「ウェブTV」を発売。市場が本格的に育つ可能性が出てきている。
デジタルカメラも日本の独壇場だ。オリンパス光学工業などのカメラ会社に家電メーカー各社、カシオ計算機、セイコーエプソンといった異業種までが参入、熾烈な新製品開発競争を繰り広げている。九七年には市場規模が百万台を突破した。
ゲイツ会長など米ハイテク企業のトップから見れば、日本企業にはサイバースペースで力を発揮する技術、ノウハウの種がふんだんにある。頻繁に訪日するのは、日本の存在感の高さの証明でもある。
「キャラクター」を生み出す力
サイバースペースで日本が優位にたちそうな要素は、家電の強さのほかにさらに二つある。
第一がモバイル(移動)端末の急速な普及である。
携帯電話はサービスの開始(一九七九年三月)から十五年近くはパッとしなかったが、この二、三年、驚異的な伸びを続けている。昨年十月末段階で携帯・PHSを合わせた契約台数は約三千四百万、人口当たりの普及率は二六%と米国(一七%)を大きく上回った。人口の少ない北欧の一部を除けば、普及率は世界一になってきている。
携帯電話の用途は音声通話だけではない。PHSのデータ送信能力は毎秒三十二キロバイトに達しており、手元の携帯型パソコンと組み合わせれば、出先からでも容易に本社などとデータのやり取りができる。さらに、自動車の〝標準装備〟になりつつあるカーナビゲーションシステムが加わってくる。カーナビもまた、日本が独壇場の世界だ。
これまでサイバースペースの主役は机の上にどんと置かれたデスクトップパソコンだった。だが、携帯電話やカーナビなど移動端末の普及から、サイバースペースは端末自体が空間的に動き回る世界へと進化してくる可能性が高い。
慶応大学の石井威望教授は、その流れをネットワークと移動体(フットワーク)が融合する「ネフットワーク」の世界ととらえている。ここで世界の先端にあるのは日本だ。
第二は映像などコンテンツ(情報の中味)事業における健闘だ。
ヒット商品が不在とされた九七年のマーケットで、「お化け」と言われるほどの人気を集めたものが三つあった。任天堂のゲームソフト「ポケットモンスター(ポケモン)」、バンダイの電子携帯ペット「たまごっち」、そしてアニメの「もののけ姫」である。
ポケモンはゲームの世界を飛び出してテレビ、映画、ぬいぐるみなどの商品へと展開し、四千億円といわれるマーケットを作り出した。バンダイは九七年九月中間決算でたまごっち関連で二百五十億円の売上げを達成。「もののけ姫」も日本では不可能と言われた映画配給収入百億円の壁を突破した。
ハード大国といわれる日本は、しばしばソフトの弱さが指摘される。だが、ゲームやアニメの核となる「キャラクター」の創出とその商業化では、日本は世界の先頭を走っている。「ドラえもん」「ハローキティ」「セーラームーン」など日本で作られたキャラクターで、東南アジアを始め世界市場へ広がっているものは枚挙に暇がない。
サイバースペースが大衆化して行くのに伴って、こうしたキャラクターを持つ強みは様々な形で生きてくる。
パソコンなど端末の画面では、オーラル(発声)ではなく、イメージのやり取りでコミュニケーションがなされる。これまでも、日本人はメーカーの製品の質の良さで勝負する「モノがものを言う」形で勝負してきただけに、会話が必要でないサイバースペースでのコミュニケーションは今よりも楽になってくるかもしれない。
日本に対して、悲観論を唱えるのは簡単だ。金融システムや官僚制度の欠陥、日本的経営の行き詰まり、そして迫りくる高齢化――。こういった問題が簡単に片づくわけではないが、だからといって「一億総悲観論」に陥るのはバカげている。「独り勝ち」といわれる米国と比較しても、今まで述べてきたように日本のアドバンテージ(優位な点)はいっぱいあるのだ。
真の「社会資本」への投資を
アジア経済の成長鈍化を〝予言〟したポール・クルーグマン米MIT教授は日本経済新聞とのインタビューで、日本の不況は「九〇年ころのアメリカとも現在のアジアとも異なる」と指摘している。似ているとすれば「(世界大不況の後に来た)一九三七年の米国の不況」だという。
当時の米国は大不況の後で経済は疲弊していたが、産業の競争力は紛れもなく世界一だった。有効需要の不足がもたらした「強い国の不況」だったのだ。その後、米国は戦争という「究極のケインズ政策」によって急速に立ち直り、第二次大戦後の黄金時代を迎える。
日本が今、最も必要としているのは内需の刺激策である。橋本首相は昨年年末に二兆円減税を発表したが、これだけでは不十分だ。筆者は財政再建を一時棚上げしても、二十一世紀の日本の骨格となり得る大型社会資本への投資が必要だと考えている。分野は「通信」と「交通」という経済の二大インフラだ。
通信ではNTTなどが計画している全家庭に光ファイバーケーブルを引く「ファイバー・ツー・ザ・ホーム」への公的支援である。
自民党は二〇一〇年がメドとなっている同計画を五年前倒ししたいとの構想を発表したが、肝心の資金面については何も語っていない。費用は約二十兆円かかるものの、達成されれば日本の通信インフラは世界一になる。バブル崩壊後に公共工事に無定見に六十兆円もつぎこんだのと比べれば、はるかに将来につながる投資だ。これで通信コストが低下すれば、サイバースペース関連の日本でのビジネス離陸を大きく支援しよう。
もう一つは東京の外環高速など道路網の整備である。地価が下落している今こそ、土地の収用を進めて積年の課題を解決するときだ。大都市近郊でもスイスイと走れる安価な高速道路は、米国やドイツの豊かさの象徴でもある。例えば、道路整備で土地を提供すれば、譲渡益は所得税、相続税とも非課税、といった思い切った優遇策を出せば、買収も容易になると思われる。
筆者が九八年の日本経済について最も恐れるのは、不況下の円高である。
九五年春に一ドル=八〇円を付けた際には、「繁栄の」アジア向け輸出が景気の下支えとなった。今回はアジアは深刻な不況に沈んでおり、韓国ウォンなどは対ドルで当時の半値以下になっている。円は「アジア売り」の一環で年明け後も下落しているが、もし真の強さが再認識されて急騰すれば、アジア通貨に対してはかつてない超円高が実現する。韓国などと競合する鉄鋼、造船、半導体メモリーといった基幹製造業は悲惨な状態になりかねない。
悪夢のシナリオを防ぐ唯一の手段は日本の内需拡大である。日本メーカーの輸出ドライブを防ぎ、アジアからの輸入を拡大して貿易黒字を縮小、一ドル=一一〇円程度へ向けた緩やかな円高にもっていかなければならない。
政策的には微妙な舵取りが必要だが、内需刺激の要は、農道やダムなどではなく、二十一世紀へ向けて日本を豊かにする、との実感が湧く社会資本に投資することだ。それが日本企業と日本人に元気を蘇らせることにつながる。
このサイト上の各コンテンツの著作権は小林収メモリアルサイト制作グループもしくは、このサイトにコンテンツを提供していただいた各企業、各寄稿者に帰属します。無断転載はお断りいたします。
Copyright: 2002 Kobayashi Osamu Memorial, associated companies and writersAll Rights Reserved.
このサイトに関するお問い合わせはinfo@kobayashiosamu.net までお願いいたします。
Designed by BlueBeagle LLC
|