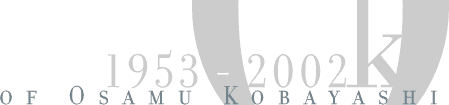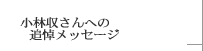|
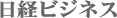
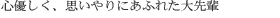

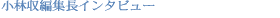

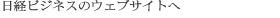
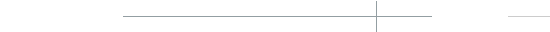
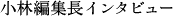
1999年06月〜08月
1999年 3月〜5月|6月〜8月|9月〜11月|12月〜00年2月
2000年 3月〜5月|6月〜8月|9月〜11月|12月〜01年2月
1999年6月7日号
上島 重二氏[三井物産社長]
総合商社は不思議な業界です。「商社不要論」「商社冬の時代」などと過去に何度も厳しい批判にさらされながら、したたかに生き抜いてきました。大学生の就職人気では、昔も今も上位にズラリと顔を並べています。
ですが、アジア危機に端を発した信用リスクの高まりとITの発展による「中抜き」は、商社にとって本当に大変な時代の到来を意味しています。兼松の大リストラは小手先の対応では未来がないことの象徴でしょう。
総合商社のルーツともいえる三井物産が、今回の長期ビジョンに沿ってどう変わっていくのか。日本経済の先行きとも絡んで目が離せません。
1999年6月14日号
後藤 卓也氏[花王社長]
企業のマネジメント力が一番磨かれる産業は、実は日用品などの身近な消費財ではないかと思っています。
自動車、電機、鉄鋼といった基幹産業では収益は市況や為替レートといった外部要因にどうしても左右されます。一方、日用品は競争は激しく単価は安め、不断の新製品開発が必要ですが、それだけに経営者の真の力量が試されます。米国でビジネススクールの教科書の常連にP&Gやジレットが入っているのは偶然ではありません。
その日本での代表は花王でしょう。成長市場からの大胆な撤退とコア事業への再集中という戦略は日本の多くの企業にも参考になりそうです。
1999年6月21日号
小林 陽太郎氏[経済同友会代表幹事・富士ゼロックス会長]
日本の経営者は国際会議などの場に出ると見劣りがする、といわれて久しいです。語学力の問題もありますが、企業経営という枠を超えて発言するには、歴史意識や文化的蓄積が十分ではないことが見逃せません。いわば教養で位負けしている格好です。
国際派経営者でなる小林会長は、おそらく彼我の差を最も痛感している1人でしょう。昨年4月、米国の経済人のためのリベラルアーツの殿堂であるアスペン研究所の日本版を発足させたのはそのためと考えられます。古典や哲学にも通じた風格ある経営者がもっと出てこないと、財界の競争力も回復しないのかもしれません。
1999年6月28日号
宮津 純一郎氏[日本電信電話社長]
インタビューを文字にする際、痛感するのはニュアンスの伝え方の難しさです。NTTの宮津社長は、その意味で最も苦労させられる1人です。グループで22万人の従業員を抱える巨大企業の理系出身トップ、といえばいかにも堅いイメージですが、語り口はざっくばらん。べらんめえ調で、言いたいことをズバズバ口にされます。
この裏表のないキャラクターが、財界だけではなく、“14年戦争”を戦った郵政省、そして政界にまで「宮津ファン」が多いことの理由でしょう。変化の時代のトップに能力が求められるのはもちろんですが、キャラクターも極めて重要になってきたようです。
1999年7月5日号
岡部 弘氏[デンソー社長]
小生が米国に駐在していた90年代の前半、日米自動車摩擦に絡んで米部品メーカーを回って驚いたことがあります。それは独立系部品の社屋の立派さでした。デーナの本社は広大な緑の芝生に建つ美術館のようで、TRW本社の庭には大きな池と鬱蒼とした森がありました。TRWの会長は一時期、日米財界人会議の米側議長を務め、部品=下請けという日本のイメージとは全く違う存在感を持っていました。
デンソーとトヨタの関係がどうなるかはともかく、部品メーカーの力の拡大は世界の潮流でしょう。従来のピラミッド型に代わる新たな協業の仕組みを考えていく必要がありそうです。
1999年7月12日号
リー・クアンユー氏[シンガポール上級相]
生真面目な表情でインタビューに答えていたリー上級相の表情が急にほころんだのは、話題がインターネットに移ったときでした。5年前に始めたとすれば、まさに「古希からのインターネット」です。それも秘書まかせなどにせず、「私はパソコンで仕事をする」と宣言して、どこに行くにも愛用のノートパソコンを手放さないとのこと。
いくつになっても最新のものにチャレンジする精神の若さの反映ですが、英国で教育を受け、英語とキーボードへの抵抗がないことも見逃せません。ネット社会が広がる中、改めて、上級相も指摘された日本での英語教育強化の必要性を感じました。
1999年7月26日号
城山 三郎氏[作家]
城山さんと関西経済界の重鎮の川上哲郎さん(住友電工前会長)は大学の同級生です。少し前にホテルで出会った時、城山さんがノートを片手に「取材の途中」と言ったところ、川上さんは驚いたとか。確かに70歳になってなお自分の足で回って作品をものするには大変なエネルギーが必要です。
その根幹にあるのは一種の健全な反骨精神だと思われます。城山さんが「どうしても断れなくて」ある役所の審議会に出たとき、ハイヤーを使わず歩いて入ろうとすると、守衛にどなられたそうです。「1回切りで、もう行かなかった」。ビジネスマンの間に城山ファンが多いのも当然でしょう。
1999年8月2日号
秋草 直之氏[富士通社長]
昨年来、何かと批判を浴びている総合電機・情報大手にあって、富士通の高評価が目立っています。先行した合理化やサービス事業へのシフトが大きいのですが、背景には時代の変化に即応してスムーズなトップ交代を実現してきたことがありそうです。
「日の丸」を背負って米IBMと対峙した時には、「陸軍士官学校」出身の山本氏、リストラを断行した90年代半ばには合理主義者の関澤氏がそれぞれ舵を取りました。ソリューションの時代のトップは自らSEの経験がある秋草氏です。時代の風を読んで次のトップを選ぶという会社の“遺伝子”が、強さの真の秘密かもしれません。
1999年8月16日号
加賀見 俊夫氏[オリエンタルランド社長]
不況から多くのテーマパークの経営が頓挫する中で、東京ディズニーランド(TDL)の強さは際立っています。それを支えている大きな理由の1つが、経営陣の「ディズニー流」に対する強烈なまでのこだわりでしょう。
実は、小生は83年の開園時に、同社の担当記者でした。忘れられないのが「おにぎり論争」です。TDLが弁当持ち込みを禁止したのに対し、「園内でおにぎりも食べられないのか」との非難が集中。その時、「夢の国のイメージを壊さないため」と退かなかったのが当時総務部長だった加賀見社長です。新商業施設でのこだわりぶりに、ふと16年前を思い出しました。
1999年8月23日号
武田 國男氏[武田薬品工業社長]
この1年ほどオーナー会社のジュニアの“受難”が続いています。ダイエー、東急建設、大和ハウス工業、タカラなど、なぜか頭文字がタ行の会社でカリスマ的な父親を継いだ息子が経営不振の責任を取らされました。
その中で全く逆のタ行の会社が武田薬品です。國男社長は眠れる獅子といわれた武田を甦らせ、「医薬品のソニー」を狙える位置へと引き上げました。その原動力は「夢にまで株価を見る」ことでしょう。もともとオーナー経営者とサラリーマン社長の最大の違いは株価意識です。武田の復活ぶりをみると、経営における良い意味でのオーナーシップの必要性を改めて感じます。
1999年8月30日号
兼子 勲氏[日本航空社長]
日本航空という会社に対する一般の印象は、ある意味でアンビバレント(愛憎併存)でしょう。国益を背負うナショナルフラッグという好印象の一方で、官僚的、非効率、人事抗争といった問題も指摘されてきました。日航がモデルとされる小説がベストセラーになるのも、そうしたイメージの2極性があるからかもしれません。
ですが、航空大競争の時代には過去のイメージは障害でしかありません。兼子社長は相談役の廃止、内部留保の吐き出しと復配、役員1年任期など思い切った改革を打ち出しました。これによって過去との完全な訣別ができるかが、日航の今後を左右しそうです。
このサイト上の各コンテンツの著作権は小林収メモリアルサイト制作グループもしくは、このサイトにコンテンツを提供していただいた各企業、各寄稿者に帰属します。無断転載はお断りいたします。
Copyright: 2002 Kobayashi Osamu Memorial, associated companies and writersAll Rights Reserved.
このサイトに関するお問い合わせはinfo@kobayashiosamu.net までお願いいたします。
Designed by BlueBeagle LLC
|