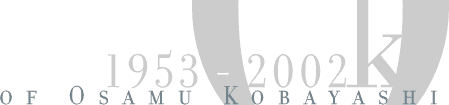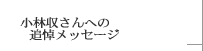|
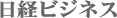
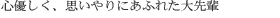

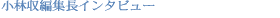

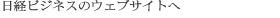
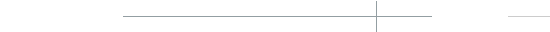
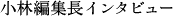
2000年09月〜11月
1999年 3月〜5月|6月〜8月|9月〜11月|12月〜00年2月
2000年 3月〜5月|6月〜8月|9月〜11月|12月〜01年2月
2000年9月4日号
和田 勇氏[積水ハウス社長]
あらゆる商品の中で、購入する時に一番こだわるもの、と聞けばほとんどの方が「家」と答えるでしょう。特にバブル崩壊で土地神話が無くなってからは、上物である「住宅」に一層の関心が集まっています。欠陥住宅問題が大きな騒ぎになったのも、この商品の特殊性ゆえでしょう。
その意味で、和田さんが顧客満足(CS)で会社を染め上げようとしておられるのは、合点がいきます。CSの数値化、一定のマニュアル化という経営学的アプローチには異論を唱えられましたが、「CSは泥臭いものですわ」という発言に第一線の営業マン上がりらしいある種の矜持を感じました。
2000年9月11日号
松浦 晃一郎氏[国連教育科学文化機関(ユネスコ)事務局長]
日本の経営者にとって一番難しいのは外国人のマネジメントでしょう。あのソニーですら、買収したハリウッドの映画会社を軌道に乗せるのに大変な苦労をしました。言葉と文化の壁はそれほど大きいのですが、中で意外に善戦しているのが国際機関のトップです。国連難民高等弁務官の緒方貞子氏、国際電気通信連合の内海善雄氏、そして松浦さんと3人を数えます。
松浦さんは1人のお付きも連れずにインタビューの場に来ました。ユネスコ事務局長に就任時も、日本人から側近を選ぶことは全くありませんでした。自分個人の力量への静かな自信が国際舞台での活躍のカギのようです。
2000年9月18日号
船井 哲良氏[船井電機社長]
新大阪駅から東海道線、大阪環状線、片町線と乗り継いだ先の住道すみのどう駅からタクシーでさらに約10分。船井電機の本社は何とも辺鄙な場所にありますが、わざわざ来た甲斐があるインタビューでした。ブランド、販売網、情報技術(IT)などが弱くても、経営者と従業員の知恵とこだわりでこれだけの高収益を上げられるというのは、日本の中堅製造業には福音でしょう。
弊誌には昔から、「知られざる会社」を特集(カバーストーリー)で取り上げるという“伝統”があります。菱食、しまむら、ロームなどがその例ですが、船井電機もいずれ「誰もが知る強い会社」になるかもしれません。
2000年9月25日号
志太 勤氏[シダックスグループ代表、ニュービジネス協議会会長]
オーナー経営には元気な会社が多いと言われます。迅速な意思決定と大胆なリスクテークという特徴が、スピード重視のドッグイヤーに合っているのでしょう。「任期中は大過無く」と考えて問題を先送りしがちな凡百のサラリーマンとは、違いが一段と鮮明になってきました。そんなオーナーたちが、志太さんをはじめとしてNBCのような舞台を通してもっと発言することが重要になってきています。
今号の「ビジネススペシャル」でも逆境を立て直した3人のオーナー経営者を登場させました。こうしたアニマルスピリッツの発揮が、日本の閉塞状況を突破するカギだと思います。
2000年10月2日号
久保利 英明氏[弁護士]
今回、取材班を組んで一連の不祥事企業等を取材して分かったのは、日本企業のリスク管理がいかに甘くなっているか、でした。そごうも雪印も決して他人事ではありません。久保利さんが「バブルぼけ」と看破したように、日本全体に病は広がっています。
1つの理由は久保利さんが「昔はノーリスクだったが、今やハイリスク」という3つの行動パターンでしょう。「同業他社がやっているから」「前例があるから」「役所が了解しているから」。これらに共通するのは、判断の基軸が他人任せだということです。当然中の当然ですが、まず自分で考えることがリスク管理の基本なのです。
2000年10月9日号
八幡 滋行氏[スミダコーポレーション社長]
今から十数年前、中国・広東省に進出してきたスミダ電機の工場を見たときの驚きはいまだに鮮明です。珠江デルタの農村地帯の真ん中に巨大な建物がたち、長い生産ラインでは膨大な数の若い中国人女性が一心に手作業していました。小生が中国のマンパワーの威力を初めて認識した瞬間でした。
日本企業が21世紀に向けて生きていくには、この隣国の巨大な労働力を使いこなすことが不可欠です。日本ではとかく「異端」と見られやすいスミダの経営ですが、「小さなグローバル企業」である同社のヒトのマネジメントには、多くの企業にとって参考になるものがありそうです。
2000年10月16日号
森本 敏氏[拓殖大学教授]
どうしてこうなったのか。日本の大きな外交案件がただでさえ慌ただしい世紀末の3カ月に集中してやってきました。ロシア、北朝鮮、韓国、そして中国。それぞれ関連する大きな外交問題に何らかの筋道を立てた上で、日本は米次期政権との交渉に臨まねばなりません。本当は、国会を空転させている暇などないはずです。
日本の外交手段が今のところODA以外にないのは悲しい現実ですが、それならその効率利用を図るべきでしょう。北東アジア情勢が大きく動き出している今、国益、国家戦略といった大問題をきちんと考えておかなければ日本は危ないと感じています。
2000年10月23日号
スティーブ・バルマー氏[マイクロソフト社長兼最高経営責任者(CEO)]
企業イメージはトップ交代で大きく変わり得ますが、ビル・ゲイツからスティーブ・バルマーというのはかなりの大変化です。天才肌で気難しい永遠のパソコン少年といったゲイツ氏に対し、バルマー氏は豪放な営業マンのイメージ。今回のインタビューをそのまま写せば、(笑)のマークが10回は入ったでしょう。トップ交代がマイクロソフトの戦略にも徐々に影響を与えてくると思われます。
とはいえ、一時代の覇者が次の時代にも勝ち続けるのは大変です。司法省との裁判ではやや優位に立った感もある同社ですが、盛者必衰の法則を打ち破れるか。ここからが正念場です。
2000年10月30日号
岩沙 弘道氏[三井不動産社長]
不動産会社には文字面のごとく「保守的」というイメージが強いのですが、三井不動産の遺伝子はちょっと違うようです。古くは超高層の霞が関ビル、また東京ディズニーランドに至る湾岸埋め立て事業など、新しいものに挑戦する風土があります。三菱地所の「丸の内」のような安定収益源を持っていないのも理由でしょうが、今の時代にこのカルチャーは貴重です。
日本では土地神話が崩れた後、それに変わるルールがまだ育たず、市場は混迷状態にあります。不動産投信の解禁が市場活性化にどこまでつながるのか。日本経済全体の先行きにとっても、これは大きなテーマだと思います。
2000年11月6日号
尹 鍾龍氏[サムスン電子副会長兼CEO]
サムスングループ(元の三星財閥)は創業者も2代目もそろって早稲田大学の出身。かつては、韓国の財閥の中で最も日本的経営に近い、と言われていました。それが、いわば日本を反面教師にして大復活をとげたというのは大いなる皮肉です。「偉大な過去を持ち、規模が大きく威張っている組織はなかなか変われない」という尹さんの言葉は、まさに日本の大企業が甘受しなければならない批判でしょう。
日本企業は経営の範例を欧米に求めがちですが、実は金融危機を乗り越えたアジアからも「強い会社」が次々と出ています。今度は、我々がサムスンの復活劇から学ぶ番かもしれません。
2000年11月13日号
マイクル・クライトン氏[作家]
遺伝子操作技術を量子テレポーテーションに、恐竜の棲む島を中世フランスにそれぞれ置き換えれば、『ジュラシック・パーク』と新作の『タイムライン』は小説として構造が似ています。にもかかわらず、前作以上に小生が楽しめたのは、タイムラインにおける「過去」というキーワードが優れて現代的だったためです。
バーチャル(仮想現実)な情報が氾濫するほど、人間は正真正銘の本物に憧れる。行き着くのは歴史的な文化遺産――。最先端のテクノロジーを素材として駆使するベストセラー作家のこうした発言には、IT時代を解く1つのカギがあるような気がしました。
2000年11月20日号
鳥井 信一郎氏[サントリー社長]
ヒット商品連発の元気印企業のオーナー経営者というイメージでインタビューに臨んだため、最初はちょっと戸惑いました。鳥井さんは非常に物静かで口数も多くありません。口八丁手八丁だった先代の故・佐治敬三さんとは本当に対照的でした。
しかし、その鳥井さんの下でサントリーは「オールド神話崩壊」を乗り越え、「超酒類企業」に変身し、お荷物と言われたビールまで黒字化しそうというから大したものです。鳥井さんは強さの源泉として何度も「現場主義」を口にされました。非公開のオーナー企業でそれが骨肉化していることが他社にない活気の秘密かもしれません。
2000年11月27日号
張瑞敏チャンルイミン氏[海爾(ハイアル)集団・首席執行官=最高経営責任者]
経営者にインタビューしてこれほど驚いたことはありません。かつてのドイツ植民都市の香りが残る青島で会った海爾のトップは、まさに「世界標準」の経営者でした。聞けば、このインタビューの直前にスイスのビジネススクールで講演してきたとか。こうした人材が出てくるところが、13億人の人口を持つ中国の凄さでしょう。
特集に寄稿いただいた田中直毅さんとは、小生は香港駐在時代以来15年近いお付き合いですが、「中国の変化の速さは想像以上」という点で意見が一致しました。「龍のリズム」がどういうものかを知るために、読者の方にも早くの訪中をお勧めします。
このサイト上の各コンテンツの著作権は小林収メモリアルサイト制作グループもしくは、このサイトにコンテンツを提供していただいた各企業、各寄稿者に帰属します。無断転載はお断りいたします。
Copyright: 2002 Kobayashi Osamu Memorial, associated companies and writersAll Rights Reserved.
このサイトに関するお問い合わせはinfo@kobayashiosamu.net までお願いいたします。
Designed by BlueBeagle LLC
|